What is 東大?
1886年(明治19年)の帝国大学令によって、東京、京都、東北、九州、北海道、大阪、名古屋および京城
と台北に相継いで官立大学が設立された。日本が先進国の仲間入りを果たすためには、優秀な人材の育成
が不可欠であり、優秀な人材を育成するためには、全国から優秀な頭脳を発掘し、総合的かつ高度な教育
を施す必要があったからである。
当時、1858年設立の慶應義塾大学(福澤諭吉の洋学塾)をはじめ、著名な私立大学の前身である学校が
既に存在していたが、これらは、東京や京都・大阪に集中しており、授業料等の諸経費も高く、事実上
“良家の子女”以外の入学は無理であった。
そこで、東京大学(江戸時代の「開成所」、「医学所」を起源とする日本最古の大学)、大阪大学(前
身は1969年設立の「大阪医学校」)および北海道大学(前身は1876年設立の「札幌農学校」)を帝国大
学に格付けし、京都(1897年)、東北(1907年)、九州(1910年)および名古屋(1939年)に相継いで
官立の総合大学が設立された。
これらの大学では、学生は、身分や出身階層等に関係なく入学試験のみによって選抜され、設備、教授
陣等の環境整備費の大部分は公費によって賄われたから、授業料も非常に安く抑えられた。
ただし、授業料が安いといっても、当時、子弟を高等学校へ進学させるだけの財力がある家庭は限られ
ていたから(1955年の時点で、高校進学率は51.5%、大学・短大進学率は、男20.9%、女14.9%)、大
部分の大学生は、やはり一部の富裕層の子弟であった。貧乏人の子弟が大学へ行くためには、並々ならぬ
苦労が必要だったのである。
帝国大学以外の主な既存大学
|
大 学( 前 身 ) |
創立年 |
|
慶應義塾大学(洋学塾) |
1858 |
|
御茶ノ水女子大学(東京女子師範学校) |
1874 |
|
立教大学 |
1874 |
|
一ツ橋大学(商法講習所) |
1875 |
|
同志社大学(同志社英学校) |
1875 |
|
青山学院大学(耕教学舎) |
1878 |
|
法政大学(東京法学社) |
1880 |
|
専修大学(夜間2年制専修学校) |
1880 |
|
明治大学(明治法律学校) |
1881 |
|
早稲田大学(東京専門学校) |
1882 |
|
駒沢大学(曹洞宗大学林専門学本校) |
1882 |
|
中央大学(英吉利法律学校) |
1885 |
|
関西大学(関西法律学校) |
1886 |
その後、9帝大(戦後は7帝大)からは、政界、官界、財界、学会に優秀な人材が多数輩出され、日本
の発展に大きく貢献した。当初の狙いは見事に達成されたと言えよう。
ところが、最近、その頂点に立つ東京大学が、様々な批判にさらされている。経済誌「ダイヤモンド」
のアンケートによると、企業が採用したい大学生の出身大学1位は、慶應、早稲田、一ッ橋等であって東
大ではない。
私の経験であるが、ある日、上司に書類のコピーを命じられた東大卒の1年生職員が、「これは私の仕
事ではない」と言って年上の女子職員にそれを押し付け、職場の顰蹙をかった。東大卒のプライドばかり
が高く、人間の出来ていない“ヤツ”が時々見られるのである。
彼らにこのようなマイナスの側面が見られるのは、決して彼らの能力が落ちたからでも、東大の教育が
悪いからでもない。世間に、学歴と学力を取り違えた「学歴主義」が蔓延してしまったからである。
つまり、“良い大学”を卒業することが優秀性の証しとされ、出世の早道となるから、多くの家庭の親
は、自分の子供を少しでも“良い大学”に入れようとし、小学生の段階から学習塾に通わせたり家庭教師
をつけたりする。その“成果”として“良い大学”に入学できた子供は、その大学に入学できたこと自体
にプライドを持ち、それが往々にして実社会にまで持ち越されるのである。
このような「学歴社会」を作り上げてきたのは、間違いなく旧帝大とその出身者である。次の表を見て
いただきたい。これは、私の通商産業省(現経済産業省)時代に、入省してきた上級職国家公務員の出身
大学を調べたものである。
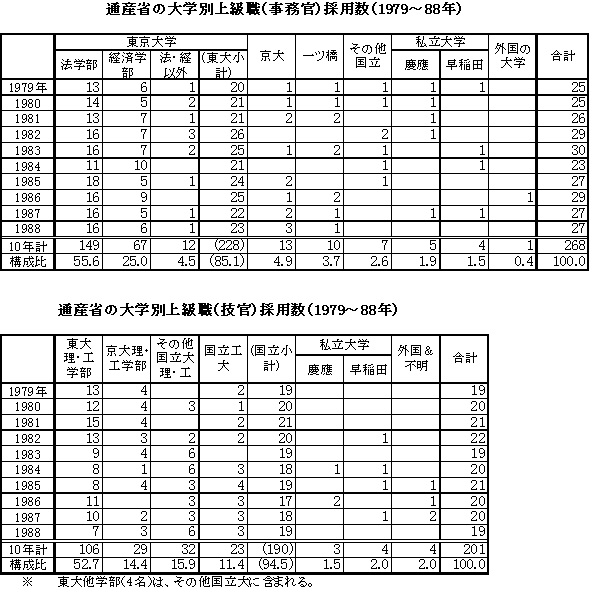 |
ご存知でない方がいるかも知れないので若干説明しておくが、役所では、上級職事務官を「Mさん」、
上級職技官を「Kさん」と言う。これは、完全無学者をAとし、昔の尋常小学校卒業者をB,戦後の6年
制小学校卒業者をCという具合に順番をつけていくと、最上位の国立大学出身・上級職事務官はMになる
。次の私立大学等出身・上級職事務官はL、その下の国立大学出身・上級職技官はK,私立大学等出身・
上級職技官はJである。IからDの間は、皆さんに考えていただきたい。
上級職の採用者は、採用時点から幹部候補生とみなされ(キャリアと言う)、一般職員(ノン・キャリ
ア)とは異なる特権的な待遇が与えられる。
通商産業省の場合、上級職以外の職員(全体の80%を占める)は、60才の定年まで勤めても、その内数
人が本省課長職級に昇進するに過ぎないが、上級職採用者は例外なく40才前後で本省課長職になり、退職
後も70才くらいまでは、役所が責任を持ってそれ相当のポストを用意してくれる(そのためには、多くの
特殊法人や公社・公団が必要である)。
ただし、同じ上級職でも事務官と技官では、相当の違いがある。K(上級職技官)の場合、本省課長職級
まではM(同事務官)とそれ程差がつかないが、局長以上に昇進する人はまれであり、ほとんどの人が本省
課長級で退職する(ここでも、多くの公社・公団等が必要になる)。要するに、官庁という職場は、徹底
した学歴社会なのである。
上記の表が示しているように、当時の通商産業省では、東大法学部という、特定大学・特定学部の出身
者がM全体の55.6%を占めていた。経済学部等の他学部を加えると、東大卒が実に85.1%に達する。
技官は事務官ほどひどくはないが、それでも東大理・工学部が過半数の52.7%を占め、国立大学が全体
の94.5%を占める。
私立大学は、慶應と早稲田から事務官・技官を含めて毎年1〜2名採用されるだけで、それ以外の大学
はゼロである。また、女性の採用は、事務官が毎年1〜2名、技官は毎年2〜3名である。
つまり、中央官庁は、単なる学歴社会ではなく、国立優位、事務官優位、男性優位の学歴社会なのであ
る。
このような「学歴社会」は、民間企業にも波及し、民間大企業も似たようなことになっている。それは、
高級官僚あるいはその卵と同じ大学の卒業生を採用することは、大蔵省(現財務省)や通産省と日常的に
接する機会を持つ大企業にとって、何かと都合が良いからである。
その結果、官・民を通じた「東大ネットワーク」とでも言うべき“集団”が形成される。この“集団”
は、情報独占を特徴とする極めて封鎖的な“集団”であり、時には、利益集団と化すことがある。
このような中で、世の親達に「学歴偏重は良くない」、「子供はもっとおおらかに育てるべきである」
と言っても、それは、お腹をすかした人の前に饅頭を置いて「食べないほうが良い」と言っているような
ものである。
昨今、教育改革あるいは大学改革をめぐって様々な議論が行われているが、「受験戦争」の根源は、こ
の学歴社会にあり、それを作り出しているのは、東大卒者を中心とする官庁機構である。
(追記) 私は、通商産業省出身なので通商産業省のことを書いたが、大蔵省と通産省は、ほぼ同じと考
えてよい。そればかりか、中央官庁に関しては、他の役所も程度の差があるだけで、似たような
ものである。例えば、教育制度の改善を声高に叫んでいる文部省の課長職以上に、何人のノンキ
ャリアがいるだろうか?「男女雇用機会均等法」を所管する労働省は、キャリア公務員として何
人の女性を採用しているだろうか?
なお、上記、通産省の上級職採用に関するデータは、1979〜88年のかなり古いものであるが、
おそらく、現在でも大きな変化はないはずである。